神経障害
更新・確認日:2024年12月19日掲載日:2018年4月6日

神経障害は糖尿病の方に最も多い合併症のひとつです。
血糖値が高い状態が続くと、しびれや痛みを感じたり、その逆に感覚がなくなるなどの障害をおこしたりすることがあります。
ここではこうした神経障害についてお話しいたします。
目次
神経障害ってどんなもの?
糖尿病の神経障害とは、どんなものでしょうか。私たちが物を触って感じるのには“感覚神経”、手足を動かすのには“運動神経”、血圧の調整や消化管を動かすのには“自律神経”が関わります。
高血糖が続くと、末梢神経の代謝に異常をきたして不必要な物質が溜まってしまったり、神経に栄養を与える血管が傷ついて血流が低下したりすることで、結果として神経の働きも障害されてしまいます。
さらに、神経障害は重篤な病気につながる場合があります。
Aさん

家でガラスを踏んで血だらけになりましたが、痛みがなくてはじめは踏んだことに気が付きませんでした。辛い症状がないので病院に行かないで様子をみていたところ、傷口が化膿して感染が広がり、病院に行ったときには足の切断が必要になると言われてしまいました。
Bさん

最近、息切れとむくみがひどくて病院に行ったところ、心筋梗塞を起こしていると言われてすぐ入院になりました。心臓の血管が詰まっていたのに、胸の痛みを感じることはなかったです。こんな重症な病気になっていたとは、気が付きませんでした。
神経障害の発症と進展を予防するために気を付けた方が良い点について知っておきましょう。
神経障害の種類
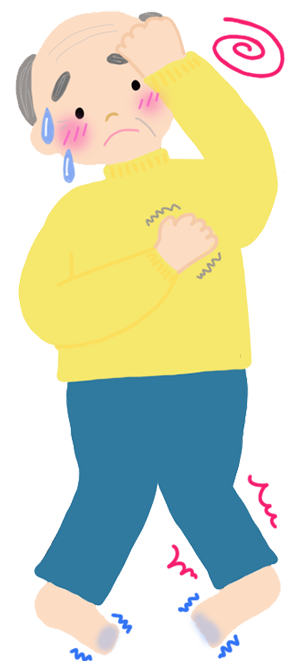
神経は多彩な働きをしているので、障害された時の症状はさまざまです。
糖尿病の神経障害でおきる症状の例をまとめました。
| 神経障害による異常 | 症状の例 |
| 感覚の異常 | 皮膚の感覚には、感覚神経が関わっています。
|
| 胃腸運動の異常 | 食べ物の消化には、自律神経が関わっています。
|
| 心臓や血圧調節の異常 | 心臓にも感覚神経があります。また、血圧の調整には自律神経が関わっています。
|
| 四肢の異常 | 四肢の運動神経の障害で、筋力低下や筋萎縮がおきることがあります。
|
| 眼や顔面の異常 | 顔面の動きや感覚、眼球運動には脳神経が関与しています。この神経が障害されると以下の症状につながります。
|
| 泌尿器・生殖器系の異常 | 骨盤にある膀胱や生殖器の働きには自律神経が関わっています。
|
| 発汗障害 | 汗の分泌には自律神経が関わっています。
|
| 血糖コントロールに影響する異常 | 低血糖の症状出現や胃腸運動には自律神経が関わります。
|
神経障害の診断
神経障害では、上で述べたようにさまざまな症状がでるので、まずは困っている症状について詳しく問診します。また、下の表にある検査を行います。
神経の障害は、糖尿病以外の病気(例えば、脊柱管狭窄症や頸椎症・腰椎症、脳梗塞など)でも生じるため、糖尿病以外の病気による症状でないことを確認することもあります。
神経障害の検査
| 検査の種類 | 内 容 |
| アキレス腱反射 | 腱反射用のハンマーでアキレス腱を叩き、正常な反射が出るか確認します。 運動・感覚神経障害の指標になります。 |
| モノフィラメント検査 | プラスチックのフィラメントで足底や足背を軽くさわり、感覚があるかどうか確認します。感覚障害の指標になります。 |
| 振動覚検査 | 音さを震わせて踝の内側にあてて、振動を感じるかどうか、何秒間振動を感じ続けるか確認します。感覚障害の指標になります。 |
| 心拍変動検査 | 心電図検査のひとつです。心臓の拍動回数は、息を吸う時と吐く時で変化します。このような呼吸に伴う心拍のゆらぎは自律神経がコントロールしているので、心拍の変動が弱い場合には自律神経障害があることが疑われます。 |
| 神経伝導検査 | 皮膚の上から神経を電気で刺激し、刺激の伝わる速度などを観測します。電気の刺激を与えるので、少し痛みを伴う検査です。 症状のない糖尿病神経障害の診断を行うのに有用です。 |
神経障害の治療
痛みに対しての治療
軽症であれば血糖コントロールや生活習慣の改善を行います。痛みが軽度の場合には非ステロイド性消炎鎮痛剤を使用します。中程度以上の痛みがある場合は、三環系抗うつ薬、プレガバリン(商品名 リリカ)、デュロキセチン(商品名 サインバルタ)などを使用します。
また、中等度以下で発症からまだ日が浅い方の場合は、アルドース還元酵素阻害薬(エパルレスタット、商品名 キネダック)という薬で進展が抑えられるという報告もあります。
自律神経障害に対しての治療
軽症の場合は、血糖コントロールと生活習慣の改善でよくなることが多いです。日常生活に影響があるほど症状が強い場合は、症状に合わせた対応をします。
- 起立性低血圧には、なるべく血圧を下げる薬は使わないようにします。急に立ち上がったりするなどの体位の変化で血圧が下がりやすいので、ゆっくり動くように心がけます。
- 消化管の動きが鈍い場合は、食事は少量を頻回に食べる様にしたり、脂肪や繊維の多い食べ物を控えたりします。また、消化運動を促進するお薬を使用する場合もあります。症状にあわせて、便秘のお薬や下痢止めの薬を使用することもあります。
- 排尿障害や勃起障害については、症状を緩和するお薬を使用する場合があります。
- 無自覚性低血糖については、低血糖が起きやすいタイミングを確認し、心配な場合はこまめに血糖測定を行ったり、適切に間食をとりいれたりして出来る限り低血糖を避ける工夫をします。
四肢の麻痺、眼球運動や顔面神経の麻痺
神経の栄養血管が閉塞し、局所的に神経障害がおきて症状につながります。血糖コントロールとは関係なく、自然に治ることが多いため、経過をみることが多いです。血管閉塞のリスクとなる動脈硬化予防のため、血糖コントロールや生活習慣を見直します。
神経障害の予防
糖尿病神経障害は、高血糖による神経細胞の変化と、動脈硬化を介した神経細胞への血流不足(栄養不足)から生じます。そのため、神経障害の予防は血糖コントロールと動脈硬化予防の両方を行うことが重要です。具体的には、以下のものが糖尿病神経障害の発症や進展と関連があるとされており、生活習慣の改善を心がけます:
・血糖コントロールの不良
・高血圧
・脂質異常
・喫煙
・飲酒
血糖コントロール、血圧や脂質異常症などの治療についてはこちらをご覧ください。
また、糖尿病罹病期間(糖尿病を発症してからの年数)は神経障害の発症と関連があるため、まだ糖尿病になっていない方に関しては糖尿病にならない、若しくは糖尿病になる時期を遅くするということが、当然ですが糖尿病神経障害の発症予防につながります。
神経障害の方に気を付けてほしいこと
- 感覚障害や足の変形がある方は、足病変になりやすくなります。フットケアについてよく理解し、足の傷や感染が心配な時は早めに受診しましょう。
- 定期的な心電図の確認も大切です。健康診断を受診しましょう。
- 自律神経障害による立ちくらみやふらつき症状がある方は、お薬の見直しが必要な場合がありますので、主治医に相談しましょう。
- 神経障害がすすんだ方は無自覚で低血糖を起こしやすい場合があります。低血糖の対応をしっかり確認すると共に、主治医と相談しながら糖尿病薬を調整しましょう。
- 神経障害をおもちの方は、網膜症や腎症の発症や進展につながると言われています。定期的に受診し、糖尿病の他の合併症についてもチェックするようにしましょう。

参考文献
- 日本糖尿病学会 編著:糖尿病診療ガイドライン2024. 南江堂, 2024
- Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the American Diabetes Association Diabetes Care 2017;40:136–154